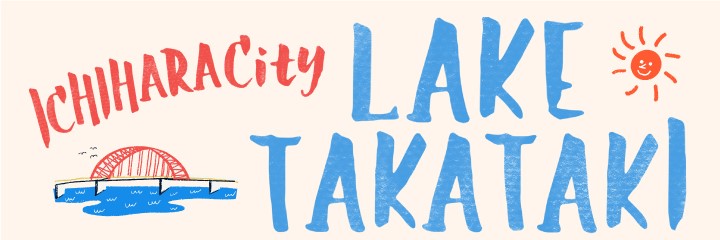「試展ー白州模写 <アートキャンプ白州>とは何だったのか」 の開幕を記念して、シンポジウムを開催いたしました。
日時:2022月10月29日(土)13:30~15:00
会場:市原湖畔美術館 多目的ホール
出演:田中泯、名和晃平、巻上公一、北川フラム(市原湖畔美術館 館長)
司会:前田礼(市原湖畔美術館 館長代理)

シンポジウムの様子
「試展ー白州模写 <アートキャンプ白州>とは何だったのか」 オープニングシンポジウム レポート
レポート2022.12.01
なぜ、市原湖畔美術館で「白州展」なのか
前田:
去年の今頃、フラムさんが「白州をやるぞ」と言い出して、その暮れに田中泯さんと石原淋さんをplan-Bにお訪ねし、今年3月にお住まいである山梨県「桃花村」にお伺いして、そこから少しずつ準備が始まりました。半年にも満たない準備期間で進めてきたわけですが、本日、無事、開幕を迎えられてほっとしております。
まず初めに、なぜ市原湖畔美術館で白州展を開催するのか、フラムさんお話ください。
北川:
現在、市原湖畔美術館はアートフロントギャラリーが指定管理を受託しております。市原市から美術館がある南市原周辺で芸術祭をやりたいと相談があり、やり取りをしている中でこの建物を改修しなければならないという話から、伊東豊雄さんが審査委員長となってリノベーションのコンペを行い、美術作品が展示できる空間を作りました。そして、2014年に「いちはらアート×ミックス」という芸術祭を開催しました。アートフロントギャラリーは、1996年から始まり、2000年に第1回目となる「越後妻有アートトリエンナーレ大地の芸術祭」のディレクションを行っています。その当時は、白州のことはほとんど知らず、行っても何をやっているかがわかりませんでしたが、「大地の芸術祭」をやっていく中で、白州は僕らよりもずっと先に農業をベースに踊りを起点としてやろうとしていたことが分かりました。85年から約25年やっているということがすごい。いろんな意味で資料がまとまっておらず、それをやるのは美術館の仕事だろうと思っていました。
ただ、形にならないだろうと思って踏ん切りがつかずにいたところ、いろんな縁が重なり、実行することになりました。まずは、越後妻有里山現代美術館 MonET(「大地の芸術祭」主要施設)で名和晃平さんに仕事をやっていただいた縁で、インタビューをしました。その時、大学生の頃から10年近く白州に通っていた、言ってみれば「こへび隊」のようなことをしていたという話をされました。また、その頃、今年の「大地の芸術祭」に向けて中谷芙二子さんにMonETのプールで霧の彫刻をやっていただきたいとお願いをしたら、それならば、田中泯さんに踊っていただきたいということがありました。巻上公一さんには、今年の「大地の芸術祭」でカバコフの《手をたずさえる塔》で演奏会をやっていただきました。カタログに書きましたが、私は、物と人間の関係を表す方法が美術だと思っていますから、名和さんがやられている仕事はそのど真ん中をやっていると思っています。名和さんにディレクションをやっていただければ、白州展はなんとか形になるのではないだろうかと思ったわけです。田中泯さんにも協力していただいて、資料も全部出していただいて、皆さんが白州をオープンにしていきたいという気持ちがあったからこうして形となりました。
今、白州が何をやろうとしていたか、どういう風になったかという出発地点をやったわけで、これから白州の意味が広がっていくきっかけになりたいと思っているのが今回のカタログです。この先、いろんな人たちが自分の中に持っている白州体験を語ると思います。それが、今後、この世の中ではすごく大きな意味を持ってくるだろうと思っています。
皆さんのおかげでできました。ありがとうございました。
前田:
最初、資料がなく、インターネットでも見つからず、美術図書館に行ってやっと白州のガイドブックを見つけ、それをコピーすることから始まりました。なんで資料がないんだろうと思っていましたが、泯さんが何も残さないとおっしゃっていたことを名和さんの文章で知りました。昨年の12月の暮れに泯さんのところを訪ねてこういう展覧会をやりたいとお話をしてOKと言っていただいたわけですが、今考えるとそれはすごいことだったんだなと思っています。
泯さんは、この半年余り私たちが準備をするのに伴走していただきましたが、今日、展覧会をご覧になりまして、どのように思っていらっしゃるのでしょうか。
田中:
残さないって、パッケージしちゃおうと思っていたわけでも、隠そうとしていたわけでもなく、誰も言い出さなかっただけの話です。ものすごい数の人たちが関わっていたわけですけれども、これまでこういうことが起きませんでした。言葉として自分の中に生まれたこと、そういうものが実感と共に自分の中で生き続けているということがありまして、なにも終わっていないという感覚が強いです。今回、こういうお話がなければ、このまま消えて行ったと思います。僕自身はそれでもいいと、今でも思っています。
この展示、ポスターや映像、作品を見たりして、感じたことや、当時に話したこととか、誰がいたとか、ものすごい量のものが今でも押し寄せていまして、全然、整理がつきません。その整理をすることをしたいと全く思わない、それを言葉で上手く言う気もないんです。
展示もすごいんです。ひとつひとつが、かつてあったということでは済まされないような存在を放っていて、とっても驚いています。だからこそ、僕自身は新しい感覚に襲われていてやべぇなという感じで今おります。
前田:
名和さんは、18歳の夏から白州に通われていたわけですけれども、今回、白州展のキュレーションをされるということで、どのような思いで臨まれたのでしょうか。
名和:
今回のきっかけは、フラムさんとのトークでした。昨年、越後妻有里山現代美術館 MonETで《Force》という、天井から床めがけて黒いシリコーンオイルが雨のように降り注ぎ続けるインスタレーションを制作したのですが、その時のトークで、白州が話題に上りました。白州は、僕が学生時代に芸術を学んだ、衝撃の体験でした。当時、美大生だった僕は「毎年、夏になると、アーティストや建築家、ダンサー、ミュージシャンといったさまざまな人たちが集まって、キャンプをしながら面白いことをやっている」という話を聞いて、京都の仲間を誘って行ってみたのです。白州には「美術家の家」というのがあって、今回も出展されている高山さん、榎倉さん、剣持さん、遠藤さん、原口さんといった作家さんたちが生活していらっしゃいました。僕はボランティアとして関わりながら、そうした作家さん同士の話を聞いたり、泯さんや木幡さんとちょっとでも話せたらいいなと思いながら毎年、手伝っていました。その頃の僕は、白州で体験したことが何だったのかもわからず、ただただ圧倒されるばかりでした。そして当然、それが将来、何になるかもわかりませんでした。しかしそれでも、白州の体験はずっと自分の中に残っていて、いまだに折に触れて思い出します。今は建築や舞台美術などにも関わっていますが、そうしたすべての原点に白州があるように思っています。
フラムさんに推薦していただいたものの、最初は白州の錚々たる面々を前に怖気づいていました。でも、実際に出展される作家さんに会ったり、剣持さんの「新作をつくる」という言葉を聞いたりする中で、徐々に勇気づけられていきました。特に、夏に泯さんが美術館にいらっしゃたんですが、その際に「当時の白州の作家だけでなく、もっと若い世代がいてもいいんじゃないか」とおっしゃってくれたんです。それがきっかけで、単なる過去のアーカイブではなく、白州というものがいかに今に受け継がれているのかを表現しよう、と気持ちが切り替わりました。そこで、展示の1ヶ月前ではあったのですが、当時一緒に白州にボランティアで参加していた藤崎了一さんや藤元明さんといった、僕が「白州らしいな」と思う作家に声をかけて参加してもらいました。その結果、どんどん展示が活性化して面白くなっていきました。やはり、過去と現在といったさまざまな要素が会場の中で衝突していったことで、当時の白州の混とんとした感じが展示空間にあらわれてきたのではないかと思います。
前田:
泯さんが「白州は今も続いている」と言ってくださったのが大きかったですね。始めは野外美術工作物「風の又三郎」の立ち上げにかかわった5人の作品の展示をやることは決まっていて、それから、いかに名和さんのキュレーションにしていくのかが、この2か月だったと思います。今回、名和さんと仕事をご一緒させていただきまして、Sandwichの皆さんのチームワークがとても素晴らしくて、多くの事を学ばせていただきました。昨日も夜遅くまで展示の調整をしてくださっていたわけですけれども、名和さんは白州で共同作業や共同生活をされていて、同時代、同世代のアーティストとも繋がっている、白州から生まれてきたアーティストだなと思いました。
名和:
Sandwichは2009年から運営しているのですが、これは僕個人のスタジオではなく、さまざまな人が立ち寄りながら新しいものを生み出していくプラットフォームとして構想しました。京都の宇治川沿いの長閑な農地にあって、そこに美術家や建築家、ダンサーや振付家、ミュージシャンといったさまざまな人々が来て、日々創作活動を行なっています。このようにSandwichの活動も、僕の中ではどこかで白州と繋がっています。そうした背景を伝える意味でも、今回の展示はいい機会でした。普段スタッフたちに話しても、なかなか全部は伝えられないですからね。
去年の今頃、フラムさんが「白州をやるぞ」と言い出して、その暮れに田中泯さんと石原淋さんをplan-Bにお訪ねし、今年3月にお住まいである山梨県「桃花村」にお伺いして、そこから少しずつ準備が始まりました。半年にも満たない準備期間で進めてきたわけですが、本日、無事、開幕を迎えられてほっとしております。
まず初めに、なぜ市原湖畔美術館で白州展を開催するのか、フラムさんお話ください。
北川:
現在、市原湖畔美術館はアートフロントギャラリーが指定管理を受託しております。市原市から美術館がある南市原周辺で芸術祭をやりたいと相談があり、やり取りをしている中でこの建物を改修しなければならないという話から、伊東豊雄さんが審査委員長となってリノベーションのコンペを行い、美術作品が展示できる空間を作りました。そして、2014年に「いちはらアート×ミックス」という芸術祭を開催しました。アートフロントギャラリーは、1996年から始まり、2000年に第1回目となる「越後妻有アートトリエンナーレ大地の芸術祭」のディレクションを行っています。その当時は、白州のことはほとんど知らず、行っても何をやっているかがわかりませんでしたが、「大地の芸術祭」をやっていく中で、白州は僕らよりもずっと先に農業をベースに踊りを起点としてやろうとしていたことが分かりました。85年から約25年やっているということがすごい。いろんな意味で資料がまとまっておらず、それをやるのは美術館の仕事だろうと思っていました。
ただ、形にならないだろうと思って踏ん切りがつかずにいたところ、いろんな縁が重なり、実行することになりました。まずは、越後妻有里山現代美術館 MonET(「大地の芸術祭」主要施設)で名和晃平さんに仕事をやっていただいた縁で、インタビューをしました。その時、大学生の頃から10年近く白州に通っていた、言ってみれば「こへび隊」のようなことをしていたという話をされました。また、その頃、今年の「大地の芸術祭」に向けて中谷芙二子さんにMonETのプールで霧の彫刻をやっていただきたいとお願いをしたら、それならば、田中泯さんに踊っていただきたいということがありました。巻上公一さんには、今年の「大地の芸術祭」でカバコフの《手をたずさえる塔》で演奏会をやっていただきました。カタログに書きましたが、私は、物と人間の関係を表す方法が美術だと思っていますから、名和さんがやられている仕事はそのど真ん中をやっていると思っています。名和さんにディレクションをやっていただければ、白州展はなんとか形になるのではないだろうかと思ったわけです。田中泯さんにも協力していただいて、資料も全部出していただいて、皆さんが白州をオープンにしていきたいという気持ちがあったからこうして形となりました。
今、白州が何をやろうとしていたか、どういう風になったかという出発地点をやったわけで、これから白州の意味が広がっていくきっかけになりたいと思っているのが今回のカタログです。この先、いろんな人たちが自分の中に持っている白州体験を語ると思います。それが、今後、この世の中ではすごく大きな意味を持ってくるだろうと思っています。
皆さんのおかげでできました。ありがとうございました。
前田:
最初、資料がなく、インターネットでも見つからず、美術図書館に行ってやっと白州のガイドブックを見つけ、それをコピーすることから始まりました。なんで資料がないんだろうと思っていましたが、泯さんが何も残さないとおっしゃっていたことを名和さんの文章で知りました。昨年の12月の暮れに泯さんのところを訪ねてこういう展覧会をやりたいとお話をしてOKと言っていただいたわけですが、今考えるとそれはすごいことだったんだなと思っています。
泯さんは、この半年余り私たちが準備をするのに伴走していただきましたが、今日、展覧会をご覧になりまして、どのように思っていらっしゃるのでしょうか。
田中:
残さないって、パッケージしちゃおうと思っていたわけでも、隠そうとしていたわけでもなく、誰も言い出さなかっただけの話です。ものすごい数の人たちが関わっていたわけですけれども、これまでこういうことが起きませんでした。言葉として自分の中に生まれたこと、そういうものが実感と共に自分の中で生き続けているということがありまして、なにも終わっていないという感覚が強いです。今回、こういうお話がなければ、このまま消えて行ったと思います。僕自身はそれでもいいと、今でも思っています。
この展示、ポスターや映像、作品を見たりして、感じたことや、当時に話したこととか、誰がいたとか、ものすごい量のものが今でも押し寄せていまして、全然、整理がつきません。その整理をすることをしたいと全く思わない、それを言葉で上手く言う気もないんです。
展示もすごいんです。ひとつひとつが、かつてあったということでは済まされないような存在を放っていて、とっても驚いています。だからこそ、僕自身は新しい感覚に襲われていてやべぇなという感じで今おります。
前田:
名和さんは、18歳の夏から白州に通われていたわけですけれども、今回、白州展のキュレーションをされるということで、どのような思いで臨まれたのでしょうか。
名和:
今回のきっかけは、フラムさんとのトークでした。昨年、越後妻有里山現代美術館 MonETで《Force》という、天井から床めがけて黒いシリコーンオイルが雨のように降り注ぎ続けるインスタレーションを制作したのですが、その時のトークで、白州が話題に上りました。白州は、僕が学生時代に芸術を学んだ、衝撃の体験でした。当時、美大生だった僕は「毎年、夏になると、アーティストや建築家、ダンサー、ミュージシャンといったさまざまな人たちが集まって、キャンプをしながら面白いことをやっている」という話を聞いて、京都の仲間を誘って行ってみたのです。白州には「美術家の家」というのがあって、今回も出展されている高山さん、榎倉さん、剣持さん、遠藤さん、原口さんといった作家さんたちが生活していらっしゃいました。僕はボランティアとして関わりながら、そうした作家さん同士の話を聞いたり、泯さんや木幡さんとちょっとでも話せたらいいなと思いながら毎年、手伝っていました。その頃の僕は、白州で体験したことが何だったのかもわからず、ただただ圧倒されるばかりでした。そして当然、それが将来、何になるかもわかりませんでした。しかしそれでも、白州の体験はずっと自分の中に残っていて、いまだに折に触れて思い出します。今は建築や舞台美術などにも関わっていますが、そうしたすべての原点に白州があるように思っています。
フラムさんに推薦していただいたものの、最初は白州の錚々たる面々を前に怖気づいていました。でも、実際に出展される作家さんに会ったり、剣持さんの「新作をつくる」という言葉を聞いたりする中で、徐々に勇気づけられていきました。特に、夏に泯さんが美術館にいらっしゃたんですが、その際に「当時の白州の作家だけでなく、もっと若い世代がいてもいいんじゃないか」とおっしゃってくれたんです。それがきっかけで、単なる過去のアーカイブではなく、白州というものがいかに今に受け継がれているのかを表現しよう、と気持ちが切り替わりました。そこで、展示の1ヶ月前ではあったのですが、当時一緒に白州にボランティアで参加していた藤崎了一さんや藤元明さんといった、僕が「白州らしいな」と思う作家に声をかけて参加してもらいました。その結果、どんどん展示が活性化して面白くなっていきました。やはり、過去と現在といったさまざまな要素が会場の中で衝突していったことで、当時の白州の混とんとした感じが展示空間にあらわれてきたのではないかと思います。
前田:
泯さんが「白州は今も続いている」と言ってくださったのが大きかったですね。始めは野外美術工作物「風の又三郎」の立ち上げにかかわった5人の作品の展示をやることは決まっていて、それから、いかに名和さんのキュレーションにしていくのかが、この2か月だったと思います。今回、名和さんと仕事をご一緒させていただきまして、Sandwichの皆さんのチームワークがとても素晴らしくて、多くの事を学ばせていただきました。昨日も夜遅くまで展示の調整をしてくださっていたわけですけれども、名和さんは白州で共同作業や共同生活をされていて、同時代、同世代のアーティストとも繋がっている、白州から生まれてきたアーティストだなと思いました。
名和:
Sandwichは2009年から運営しているのですが、これは僕個人のスタジオではなく、さまざまな人が立ち寄りながら新しいものを生み出していくプラットフォームとして構想しました。京都の宇治川沿いの長閑な農地にあって、そこに美術家や建築家、ダンサーや振付家、ミュージシャンといったさまざまな人々が来て、日々創作活動を行なっています。このようにSandwichの活動も、僕の中ではどこかで白州と繋がっています。そうした背景を伝える意味でも、今回の展示はいい機会でした。普段スタッフたちに話しても、なかなか全部は伝えられないですからね。
「白州」のはじまり
前田:
白州は、あらゆる芸術のジャンルを超えた場となっていたのですが、すごく驚いたのは、音楽の人たちの豊かさです。そうした中に巻上さんもいたわけですけれども、巻上さんにとっての白州とはどういうものだったのでしょうか。
巻上:
とんでもないところですね。今も続いているということで、思い出話をしてはいけないとは思うのですが、展覧会を見ると、こんなにやっていたんだと圧倒されました。泯さんも全てを見ていない、見切れないほどのパフォーマンスをやっていました。多分、勝手にやっていた人たちもいたと思います。僕は1993年ぐらいから参加しました。その前に灰野敬二から、セシル・テイラーが、チューニングが狂ったピアノで弾いているぞ、とかいう話を聞いて、面白いフェスをやっているなと思っていました。そうしたら、吉沢元治さんというアーティストが「カンパニー」というデレク・ベイリーが考えた即興演奏のスタイルでやるというのがありまして、それに参加することになりました。これは僕にとって、とてもいい経験になりました。元々ロックバンドをやっていて、この辺りから、即興と関わるということができるようになりました。
翌年にボイスサーカスというものをやりました。竹田賢一さんが声だけでやりたいということで声をかけてくださいました。打ち合わせに行ったら竹田さんは来なくて、そこから僕がリーダーになりました。結局、一回も竹田さんは来ませんでした。白州ってすげぇなと、厳しさと緩さが共存しているところがすごいんです。
僕が集めたメンバーでない人たちが世界中から集まってきて、その中にロシア連邦のトゥヴァ共和国からアンサンブルをやる人たちが来ていました。その人たちのホーメイが本当に素晴らしくて、本当にびっくりして、栗林の中でワークショップをやってもらいました。その時に参加した中で20人くらいの人たちが来年トゥヴァに行きますと言ったのですが、行ったのは僕一人だけだったんです。でもそのおかげで、今でもトゥヴァの人たちとの交流が続いています。そのあと、毎年、呼ばれないなぁと思いながら、白州に参加していました。口琴をつくるワークショップなど、様々なことをやっていました。今の僕につながることを色々とやりました。チャンスもいただきました。
前田:
泯さんは世界的な繋がりがあって、その方々が白州にいらっしゃっていたわけですよね。その多様さにびっくりしました。
田中:
40歳の時なんですけれども、スタジオで踊りの練習をするのをもうやめないといけないなと思って白州に行きました。その当時、僕のところにきていた踊り志望人たちの3/4が外国人で、その人たちも引き連れて白州に行きました。ちょうどその頃、農業を始めた頃に、外国に行く仕事が急に増えて来て、益々外国から僕のところにきたいという若者が増えてきたタイミングでした。まさか、白州で芸術に関わることをやろうなんては思っていませんでした。その当時の仲間と土地も家も全て借りてやろうと決めていました。なかなか土地も貸してもらえず、土地を貸してもらうためには働く気があるということを見せないといけない、やる気をデモンストレーションしないといけないとやっていました。貸して貰えた土地が少ないものだから人手は余っていたので、みんなを手伝いに行かせました。お金は絶対貰わないようにしていたら、何年か経ったときに、家の土間がお米と野菜でいっぱいになって、食べるものには困らなくなりました。
その当時は、ギャラリーが画廊と言われている頃で、学生たちはナップサックを背負って、画廊を渡り歩いていました。その頃に美術を知って、美術の仲間に僕のところで踊らないかと誘われました。いっぱい友達ができました。
芸術だと思って踊っている人たちは、ある自分のセンスでチームを作ってずっと続けています。芸術家と言われている舞踊家のほとんどがそうです。僕は踊りというものはそういうものではないと決めたんです。芸術と並ぶべきものではない、つまり、私に所属していないのです。踊りなんです。誰が踊ろうが踊りは踊りなんです。それで、最初に裸で踊り始めました。6年も裸で踊りました。その流れで白州に行って、いろんなタイプの美術家たちと知り合いました。
そこに剣持さんがやってきました。東京で展示していた自分の作品を搬出しなければならないので、白州に持ってきたいと言って、剣持さんが一人で組み立て直したわけです。それを手伝いながらずっと見ていて、完成して、その後1週間くらい、天候が変わっていくなかで見ていた作品が、悪くないなと思ったのです。それがきっかけで、その当時知っていた美術家たちに連絡をして、あっという間にすごい数の美術家が白州にやってきたんです。「自分の作品を、搬入搬出の必要のない、可能な限り朽ちるまで見たくないかい?」という話から始まって、1年目の白州フェスティバルというものが、美術をきっかけにして始まりました。そこに、踊りが入り、音楽が入り、様々な芸能と呼ばれているものが入ってきました。昔は、踊りは都市にはなく、人々の労働の中や影から生まれたという考えがあったのも、白州に来たきっかけでした。そういうもので1年目が始まりました。
思い出すと本当に懐かしいです。全ての作家に自分で作れるものをここで展示しましょうと話しました。なので、みんな地下足袋をはいて、泥んこになって制作をしました。最初からいつまでやるとは決めておらず、1年が終わって、来年どうしようという話にはなるけれども、誰も話さず、翌年の春一番に、今年やるのかを決めていた。毎年、その年にやるかを決めて、やっていました。前の年、1年間に出会う人たちに声をかけて白州に来てもらっていました。実行委員会も出し物も友達同士で出来上がっているのです。単なる縁でやっています。そういう風に始まって24年が経ちました。
白州は、あらゆる芸術のジャンルを超えた場となっていたのですが、すごく驚いたのは、音楽の人たちの豊かさです。そうした中に巻上さんもいたわけですけれども、巻上さんにとっての白州とはどういうものだったのでしょうか。
巻上:
とんでもないところですね。今も続いているということで、思い出話をしてはいけないとは思うのですが、展覧会を見ると、こんなにやっていたんだと圧倒されました。泯さんも全てを見ていない、見切れないほどのパフォーマンスをやっていました。多分、勝手にやっていた人たちもいたと思います。僕は1993年ぐらいから参加しました。その前に灰野敬二から、セシル・テイラーが、チューニングが狂ったピアノで弾いているぞ、とかいう話を聞いて、面白いフェスをやっているなと思っていました。そうしたら、吉沢元治さんというアーティストが「カンパニー」というデレク・ベイリーが考えた即興演奏のスタイルでやるというのがありまして、それに参加することになりました。これは僕にとって、とてもいい経験になりました。元々ロックバンドをやっていて、この辺りから、即興と関わるということができるようになりました。
翌年にボイスサーカスというものをやりました。竹田賢一さんが声だけでやりたいということで声をかけてくださいました。打ち合わせに行ったら竹田さんは来なくて、そこから僕がリーダーになりました。結局、一回も竹田さんは来ませんでした。白州ってすげぇなと、厳しさと緩さが共存しているところがすごいんです。
僕が集めたメンバーでない人たちが世界中から集まってきて、その中にロシア連邦のトゥヴァ共和国からアンサンブルをやる人たちが来ていました。その人たちのホーメイが本当に素晴らしくて、本当にびっくりして、栗林の中でワークショップをやってもらいました。その時に参加した中で20人くらいの人たちが来年トゥヴァに行きますと言ったのですが、行ったのは僕一人だけだったんです。でもそのおかげで、今でもトゥヴァの人たちとの交流が続いています。そのあと、毎年、呼ばれないなぁと思いながら、白州に参加していました。口琴をつくるワークショップなど、様々なことをやっていました。今の僕につながることを色々とやりました。チャンスもいただきました。
前田:
泯さんは世界的な繋がりがあって、その方々が白州にいらっしゃっていたわけですよね。その多様さにびっくりしました。
田中:
40歳の時なんですけれども、スタジオで踊りの練習をするのをもうやめないといけないなと思って白州に行きました。その当時、僕のところにきていた踊り志望人たちの3/4が外国人で、その人たちも引き連れて白州に行きました。ちょうどその頃、農業を始めた頃に、外国に行く仕事が急に増えて来て、益々外国から僕のところにきたいという若者が増えてきたタイミングでした。まさか、白州で芸術に関わることをやろうなんては思っていませんでした。その当時の仲間と土地も家も全て借りてやろうと決めていました。なかなか土地も貸してもらえず、土地を貸してもらうためには働く気があるということを見せないといけない、やる気をデモンストレーションしないといけないとやっていました。貸して貰えた土地が少ないものだから人手は余っていたので、みんなを手伝いに行かせました。お金は絶対貰わないようにしていたら、何年か経ったときに、家の土間がお米と野菜でいっぱいになって、食べるものには困らなくなりました。
その当時は、ギャラリーが画廊と言われている頃で、学生たちはナップサックを背負って、画廊を渡り歩いていました。その頃に美術を知って、美術の仲間に僕のところで踊らないかと誘われました。いっぱい友達ができました。
芸術だと思って踊っている人たちは、ある自分のセンスでチームを作ってずっと続けています。芸術家と言われている舞踊家のほとんどがそうです。僕は踊りというものはそういうものではないと決めたんです。芸術と並ぶべきものではない、つまり、私に所属していないのです。踊りなんです。誰が踊ろうが踊りは踊りなんです。それで、最初に裸で踊り始めました。6年も裸で踊りました。その流れで白州に行って、いろんなタイプの美術家たちと知り合いました。
そこに剣持さんがやってきました。東京で展示していた自分の作品を搬出しなければならないので、白州に持ってきたいと言って、剣持さんが一人で組み立て直したわけです。それを手伝いながらずっと見ていて、完成して、その後1週間くらい、天候が変わっていくなかで見ていた作品が、悪くないなと思ったのです。それがきっかけで、その当時知っていた美術家たちに連絡をして、あっという間にすごい数の美術家が白州にやってきたんです。「自分の作品を、搬入搬出の必要のない、可能な限り朽ちるまで見たくないかい?」という話から始まって、1年目の白州フェスティバルというものが、美術をきっかけにして始まりました。そこに、踊りが入り、音楽が入り、様々な芸能と呼ばれているものが入ってきました。昔は、踊りは都市にはなく、人々の労働の中や影から生まれたという考えがあったのも、白州に来たきっかけでした。そういうもので1年目が始まりました。
思い出すと本当に懐かしいです。全ての作家に自分で作れるものをここで展示しましょうと話しました。なので、みんな地下足袋をはいて、泥んこになって制作をしました。最初からいつまでやるとは決めておらず、1年が終わって、来年どうしようという話にはなるけれども、誰も話さず、翌年の春一番に、今年やるのかを決めていた。毎年、その年にやるかを決めて、やっていました。前の年、1年間に出会う人たちに声をかけて白州に来てもらっていました。実行委員会も出し物も友達同士で出来上がっているのです。単なる縁でやっています。そういう風に始まって24年が経ちました。
他者の土地でものをつくる
前田:
その縁がとても豪華だなと思います。今回は、作家の展示に加えて、泯さんのコレクションが展示されています。その中には、リチャード・セラの作品やカレル・アペルのライブペインティングで作られた衣装もあります。
最初、美術の資料しかあまりなくて、象設計集団の樋口裕康さんにインタビューした際、「美術というのは一部でしかなくて、白州は、建築や音楽などのあらゆるジャンルがジャンルレスでヒエラルキーがない中でやったことがすごいことだったよ、白州は泯さんが白州に移住した1985年からダンス白州が終わるまでの24年間を通して有機体のようなものとして見ないと間違うよ」と言われたことが転換点だったと思っています。特に、美術家の人たちが、泯さんに自分で作れと言われて、土地の交渉からやっていたということが驚きでした。「他者の土地にものをつくる」ということを大地の芸術祭の10年以上も前からやっていたわけですね。
北川:
2000年の第1回大地の芸術祭のときに、その地域の馬とか牛とか豚とか鶏とかみんなに参加してもらおうと思ったんですよ、でも、上手く実現しなかった。白州はそれをやったというのを知りました。この美術館の近くには「ぞうの国」があって、ぞうの行進もやろうとしたんですが、うんちが大変で。行進はあきらめたのですが、1頭だけは連れてきたことがあります。
今この大変な時に、自然とか地球環境に感応できて、いろいろ動くことができるのは身体だと思っています。身体というのがものすごく重要であって、それが決定的です。白州は、田中泯さんというすばらしい人間、すばらしい踊りをやる人がいたということが決定的で、一般的に捉えにくいというところがあると思います。僕は作家ではない立場で、美術を自然と人間の関係であると、その関係を表現する方法だと考えてきた人間です。美術は相当面白いのに、これだけ面白くなくなっているのは何なんだろうかということで、こういう仕事を始めたところがあります。でも泯さんとはアプローチが違うところがあって、泯さんは平気でばっとやれてしまう。人の土地を借りるということは、その土地の持ち主がいて、集落の人がいてという、関係性の面倒なところから僕は入っていくわけです。言ってみれば、私有制の権化、これはいい意味で言っていますが、田んぼの持ち主にアプローチをするのにものすごい手間暇をかけながら解釈して、要するに、私有財産を打ち破るということになるんですよ。強引に、人の土地に作家のどうしようもない変な作品を置こうとするわけですから。そういう捉え方を僕はする。泯さんはそこをすっとやれてしまうのです。
田中:
いや、やれないですよ。所有者とアーティストが会話をする、これが面白いんです。そのあとに農業委員会というどうにもならない、政治の始まりがある。これが大変なんです。僕、それですごい苦労しましたよ(笑)。
北川:
関係者がおられるかもしれないのですが、政治なんて大したことないんですよ。もっと大変なのは農地なんです。水をどう配るかとか、政治なんてやわな話ではないんですよ。そこにどう関わっていくかということです。
田中:
美術家でひとり、どんどんどんどん地面を掘っていた人がいるんですよ。そしたら、水が出てきて。それで、地主に呼ばれて「おまえは地面から何メートル下まで俺が貸した土地だと思っているんだ!水が出た、もうだめだよ」と言われた。
北川:
それ(農業委員会)を新潟では土改(土木改良事務所)と言います。並みの政治権力ではない、命が掛かっていますから、本当に殴られて叩き潰される。そういう中でやっていくわけです。泯さんは体一つでそういう感じでやってしまいますが、僕はなんだかんだ、私有財産を打ち破ることであるとか言ってやっている。
田中:
沖縄に長いこと旅(ツアー)をして帰ってきたら、僕たちが借りている田んぼが、なんと、屎尿の処理をする場所になっていたんです。柵状に深く穴を掘って、そこにバキュームカーで持ってきた屎尿をそこに流し込む。その工事が終わっていたんですよ。僕は、待った!、やめてくれ!と言って、毎晩、思いっきりお酒を飲んで、お酒を飲まないと言えないから、それで、一軒一軒それに関わる人たちのところを一週間くらい周ったんです。そしたら首長さんに呼び出されて、おうちに行きました。うちの地域は、よそ者が訪ねてきたら敷居の手前で小さくなって挨拶をするのが風習としてありまして、僕もやりましたよ。顔を上げたら首長さんがにやにやしていて、「代替地はできているから、もう大丈夫だよ」と言われたんです。
その縁がとても豪華だなと思います。今回は、作家の展示に加えて、泯さんのコレクションが展示されています。その中には、リチャード・セラの作品やカレル・アペルのライブペインティングで作られた衣装もあります。
最初、美術の資料しかあまりなくて、象設計集団の樋口裕康さんにインタビューした際、「美術というのは一部でしかなくて、白州は、建築や音楽などのあらゆるジャンルがジャンルレスでヒエラルキーがない中でやったことがすごいことだったよ、白州は泯さんが白州に移住した1985年からダンス白州が終わるまでの24年間を通して有機体のようなものとして見ないと間違うよ」と言われたことが転換点だったと思っています。特に、美術家の人たちが、泯さんに自分で作れと言われて、土地の交渉からやっていたということが驚きでした。「他者の土地にものをつくる」ということを大地の芸術祭の10年以上も前からやっていたわけですね。
北川:
2000年の第1回大地の芸術祭のときに、その地域の馬とか牛とか豚とか鶏とかみんなに参加してもらおうと思ったんですよ、でも、上手く実現しなかった。白州はそれをやったというのを知りました。この美術館の近くには「ぞうの国」があって、ぞうの行進もやろうとしたんですが、うんちが大変で。行進はあきらめたのですが、1頭だけは連れてきたことがあります。
今この大変な時に、自然とか地球環境に感応できて、いろいろ動くことができるのは身体だと思っています。身体というのがものすごく重要であって、それが決定的です。白州は、田中泯さんというすばらしい人間、すばらしい踊りをやる人がいたということが決定的で、一般的に捉えにくいというところがあると思います。僕は作家ではない立場で、美術を自然と人間の関係であると、その関係を表現する方法だと考えてきた人間です。美術は相当面白いのに、これだけ面白くなくなっているのは何なんだろうかということで、こういう仕事を始めたところがあります。でも泯さんとはアプローチが違うところがあって、泯さんは平気でばっとやれてしまう。人の土地を借りるということは、その土地の持ち主がいて、集落の人がいてという、関係性の面倒なところから僕は入っていくわけです。言ってみれば、私有制の権化、これはいい意味で言っていますが、田んぼの持ち主にアプローチをするのにものすごい手間暇をかけながら解釈して、要するに、私有財産を打ち破るということになるんですよ。強引に、人の土地に作家のどうしようもない変な作品を置こうとするわけですから。そういう捉え方を僕はする。泯さんはそこをすっとやれてしまうのです。
田中:
いや、やれないですよ。所有者とアーティストが会話をする、これが面白いんです。そのあとに農業委員会というどうにもならない、政治の始まりがある。これが大変なんです。僕、それですごい苦労しましたよ(笑)。
北川:
関係者がおられるかもしれないのですが、政治なんて大したことないんですよ。もっと大変なのは農地なんです。水をどう配るかとか、政治なんてやわな話ではないんですよ。そこにどう関わっていくかということです。
田中:
美術家でひとり、どんどんどんどん地面を掘っていた人がいるんですよ。そしたら、水が出てきて。それで、地主に呼ばれて「おまえは地面から何メートル下まで俺が貸した土地だと思っているんだ!水が出た、もうだめだよ」と言われた。
北川:
それ(農業委員会)を新潟では土改(土木改良事務所)と言います。並みの政治権力ではない、命が掛かっていますから、本当に殴られて叩き潰される。そういう中でやっていくわけです。泯さんは体一つでそういう感じでやってしまいますが、僕はなんだかんだ、私有財産を打ち破ることであるとか言ってやっている。
田中:
沖縄に長いこと旅(ツアー)をして帰ってきたら、僕たちが借りている田んぼが、なんと、屎尿の処理をする場所になっていたんです。柵状に深く穴を掘って、そこにバキュームカーで持ってきた屎尿をそこに流し込む。その工事が終わっていたんですよ。僕は、待った!、やめてくれ!と言って、毎晩、思いっきりお酒を飲んで、お酒を飲まないと言えないから、それで、一軒一軒それに関わる人たちのところを一週間くらい周ったんです。そしたら首長さんに呼び出されて、おうちに行きました。うちの地域は、よそ者が訪ねてきたら敷居の手前で小さくなって挨拶をするのが風習としてありまして、僕もやりましたよ。顔を上げたら首長さんがにやにやしていて、「代替地はできているから、もう大丈夫だよ」と言われたんです。
剣持さんの「塔」
北川:
際どいことを言いにくいのですが、瀬戸内だと、言うことを聞かないとなると、平気で海に放り出されます。その問題があった上で、「表現」と言われているものがあるのです。まじめな話をすると、美術がいかにやわかというと、そこをなしに表現の話をしてしまうからです。僕は全くやわだと思うんです。
さっき、泯さんが沖縄でと言ったから、調子に乗って言うと、僕は沖縄にいっぱい塔を建てたいんです。沖縄の私有地に。それはある意味で、飛行機が飛ばせないというか、飛べない塔を作らなければならない。僕の夢です。
田中:
その話に乗る美術家はいないんですか。
名和
ぜひ、剣持さんの塔を建ててほしいですね。僕も手伝いますから。
北川:
高山さんも剣持さんも本当に今調子が良くなくて。でも、みんな頑張っている。
剣持さんなんて、展覧会の準備の最中に具合が悪くなって、少し良くなって、また最後にやりだして具合が悪くなって。でも、やっている限り頑張っているんですよ。
名和:
剣持さんは展示計画の初期から塔を建てたいとおっしゃっていて、設計や構造計算などずっと相談を進めていました。しかし最終的には「やはり美術館で塔を建てるのには違和感がある」と判断されたようで、中止になりました。当時から参加作家の方々は、白州でお酒を飲んで話をするたびに、今の美術ひいては近代の仕組みに対する不満ややるせなさをこぼしていました。だから僕は、白州の根底をなすエネルギー源として、それらに対する抵抗があるのだと感じていました。美術館やギャラリーで活動されていたアーティストがこぞって白州に集まったのも、そこに自由を感じたからだと思うのです。こうした歴史の上で、僕たちの世代は美術と社会にどう向き合うべきなのか。その模索のひとつが、今回の展覧会だと思っています。
田中:
剣持さんは、1年目に白州のきっかけになった塔を作って、2年目にも塔を建てたんです。それはとても高い塔、22mもある塔で、それを上から下までずっと自分で塗っていくんです。タールで。顔中真っ黒になって、作品のふもとで疲れて横になっていたんだけれども、その顔がにやにやしていて。その姿が僕は嬉しくて嬉しくて、やったなという気持ちになりました。それは残念ながら真ん中でぽきっと折れてしまったのですが、いつまででもここにあっていいよと話していました。
名和:
鶏小屋の上に倒れちゃったんですよね。そのあと、僕と藤崎くんでその鶏小屋の修復をやりました。(笑)
北川:
それが白州精神というか。剣持さん、人にやらせないんですよね。無理なのにやらせないんですよ。
田中:
本当に頑固な職人タイプなんです。
北川:
剣持さんに第1回目の大地の芸術祭に参加してもらったときに、僕は、白州の塔をイメージしてお願いしましたが、こともあろうか、お寺に入って、その集落の全部の家を訪ねて行って、その家にあるアルバムで何かを作るという作品を作った。決して、人にやらせないんですよ、延々と一人でやっているんですよ。本当にこれはすごいなと思います。白州でやっていたことは、ギリギリになるまで重機を使わず、自力でやる。ここで伝わっていく何かというのが、なくなってきている。大地の芸術祭と白州と比較してもしょうがないけれども、白州が持っているのは、泯さん的に言えば、誰でも作れるだろうということ。誰でも作れる場所を作っていったのが白州。大地の芸術祭は、「作ること」をやろうとした。そのすごい差があって、そこを白州から学ぶというか、私たちの時代、いろんな意味で、白州体験というものが重要だと思いました。それが、剣持さんの倒れても一人でやるというのに現れていると思います。
際どいことを言いにくいのですが、瀬戸内だと、言うことを聞かないとなると、平気で海に放り出されます。その問題があった上で、「表現」と言われているものがあるのです。まじめな話をすると、美術がいかにやわかというと、そこをなしに表現の話をしてしまうからです。僕は全くやわだと思うんです。
さっき、泯さんが沖縄でと言ったから、調子に乗って言うと、僕は沖縄にいっぱい塔を建てたいんです。沖縄の私有地に。それはある意味で、飛行機が飛ばせないというか、飛べない塔を作らなければならない。僕の夢です。
田中:
その話に乗る美術家はいないんですか。
名和
ぜひ、剣持さんの塔を建ててほしいですね。僕も手伝いますから。
北川:
高山さんも剣持さんも本当に今調子が良くなくて。でも、みんな頑張っている。
剣持さんなんて、展覧会の準備の最中に具合が悪くなって、少し良くなって、また最後にやりだして具合が悪くなって。でも、やっている限り頑張っているんですよ。
名和:
剣持さんは展示計画の初期から塔を建てたいとおっしゃっていて、設計や構造計算などずっと相談を進めていました。しかし最終的には「やはり美術館で塔を建てるのには違和感がある」と判断されたようで、中止になりました。当時から参加作家の方々は、白州でお酒を飲んで話をするたびに、今の美術ひいては近代の仕組みに対する不満ややるせなさをこぼしていました。だから僕は、白州の根底をなすエネルギー源として、それらに対する抵抗があるのだと感じていました。美術館やギャラリーで活動されていたアーティストがこぞって白州に集まったのも、そこに自由を感じたからだと思うのです。こうした歴史の上で、僕たちの世代は美術と社会にどう向き合うべきなのか。その模索のひとつが、今回の展覧会だと思っています。
田中:
剣持さんは、1年目に白州のきっかけになった塔を作って、2年目にも塔を建てたんです。それはとても高い塔、22mもある塔で、それを上から下までずっと自分で塗っていくんです。タールで。顔中真っ黒になって、作品のふもとで疲れて横になっていたんだけれども、その顔がにやにやしていて。その姿が僕は嬉しくて嬉しくて、やったなという気持ちになりました。それは残念ながら真ん中でぽきっと折れてしまったのですが、いつまででもここにあっていいよと話していました。
名和:
鶏小屋の上に倒れちゃったんですよね。そのあと、僕と藤崎くんでその鶏小屋の修復をやりました。(笑)
北川:
それが白州精神というか。剣持さん、人にやらせないんですよね。無理なのにやらせないんですよ。
田中:
本当に頑固な職人タイプなんです。
北川:
剣持さんに第1回目の大地の芸術祭に参加してもらったときに、僕は、白州の塔をイメージしてお願いしましたが、こともあろうか、お寺に入って、その集落の全部の家を訪ねて行って、その家にあるアルバムで何かを作るという作品を作った。決して、人にやらせないんですよ、延々と一人でやっているんですよ。本当にこれはすごいなと思います。白州でやっていたことは、ギリギリになるまで重機を使わず、自力でやる。ここで伝わっていく何かというのが、なくなってきている。大地の芸術祭と白州と比較してもしょうがないけれども、白州が持っているのは、泯さん的に言えば、誰でも作れるだろうということ。誰でも作れる場所を作っていったのが白州。大地の芸術祭は、「作ること」をやろうとした。そのすごい差があって、そこを白州から学ぶというか、私たちの時代、いろんな意味で、白州体験というものが重要だと思いました。それが、剣持さんの倒れても一人でやるというのに現れていると思います。
身体が関係をつくっていった
田中:
僕は、最初の頃は、参加してくれる方に、自分の踊りをなんと表現するか、なんという踊りなのか、どういう踊りを踊ろうとしているのかと聞いていました。ジャンルが決まっているのであれば、例えば、舞踏とか、コンテンポラリーとか、最初の頃はモダンダンスとか。僕は「名づけようのない踊り」を自分の踊りとしているのですが、自分の踊りの名前を流行りの言葉に所属させようとすること自体が、踊りにとって屈辱だと思うんです。本人が仮に新しいことをやりたいと思っているのであれば、名前なんてどうでもいいはずなのです。どうもそういうところで、まるで境界があるかのようにして。その時その時の流行り、流行りの源流にあるのはバレエですけれども、あれが未だに尾を引いて、バレエを習った身体が新しい踊りを踊っているということなんですよね。そこらへんを僕は、白州をやっている間ずーっと、「踊りはどうなるんだろう」というのが一番のテーマでした。もうやめようとなったのは、要するに、踊りの先行きがなくなったからです。こういう風に踊りを提案し、踊りをその土地で生まれさせてやる、それを繰り返しやっていく必要がないと思ったからです。だったらスタジオで踊りを作ればいいじゃん、くらいの投げやりな気分になりました。ちょっと好きな踊りから、他者意識というか、人のために踊りを考える気が一瞬なくなりました。自分の踊りが所属するカテゴリーをまず先に作ってしまうのです。それはないだろうと。だから、お金がないから踊れないって言ったりするんです。そんな言葉は不可能ですよ。踊りはあるものですからね。あなたが踊らなくても、踊りなんていくらでもあるよ。でも、そういう言葉で自己表明してしまうことは踊りにとって失礼なわけです。僕は白州の根底に踊りというものを置き、考え続けてきました。そこに、音楽もあり、美術もあったわけです。美術の人に対して、僕は踊りを見るようなつもりで美術が出来上がっていく姿を見ていたわけです。音楽の人にとっては、踊りが音楽に見えたりするわけです。それが一番面白い、そういう関係なんじゃないかなと思います。美術というのは、踊りが存在することで、美術という空間がどうなるんだろうかというのがすごく大きなテーマでした。自然とものとの関係だとすればですね。
名和:
当時の僕は美大の1年生で、「具体」や「もの派」が何なのかも分かっていませんでした。でも「美術家の家」で、もの派の世代の方々が「もの派というのは、ものとものの間に何かがあるということなんだ」と話しているのを聞いて、それが印象に残っていました。そのころ泯さんも「踊り手の肉体と見ている人の間にあるものが踊りなんだ」とおっしゃっていて、そこに繋がりがあるように感じられたのです。その後も僕は彫刻科で制作を続けてきましたが、そこでは単にオブジェクトをつくるだけではなく「物質と自分の身体がどう交流するか」「作品を見る人の中に何が残るのか」ということをずっと考えていました。こうした彫刻に対する意識も、白州での体験の中でつくられていったのだと思っています。
前田:
泯さんが、音楽と人、土地と人、美術と、そういうつなぎ役となっていた、身体で繋いでいく感じが面白いと思いました。
田中:
誤解されたくないのですが、僕は身体気象という言葉をだいぶ前から使っているのですが、これは、中心というものが常に空のように絶えず動いて回っている。時には消え、時には生まれているわけです。そういう人間同士のありようというのが、僕にとっては踊り的なんです。それが踊りといってもいいと思います。中心にとどまるということが僕にはありえないんです。泯さんがいたからというわけではなく、友達と縁が作り上げたものなのです。僕がやれることは僕流のやり方でやる、それがうまくハーモニーしていた、そこにやってくる若者たちもそのハーモニーに加わる。それが楽しかったんです。
今やろうとしたらとんでもない苦労をするんでしょう。
僕は、最初の頃は、参加してくれる方に、自分の踊りをなんと表現するか、なんという踊りなのか、どういう踊りを踊ろうとしているのかと聞いていました。ジャンルが決まっているのであれば、例えば、舞踏とか、コンテンポラリーとか、最初の頃はモダンダンスとか。僕は「名づけようのない踊り」を自分の踊りとしているのですが、自分の踊りの名前を流行りの言葉に所属させようとすること自体が、踊りにとって屈辱だと思うんです。本人が仮に新しいことをやりたいと思っているのであれば、名前なんてどうでもいいはずなのです。どうもそういうところで、まるで境界があるかのようにして。その時その時の流行り、流行りの源流にあるのはバレエですけれども、あれが未だに尾を引いて、バレエを習った身体が新しい踊りを踊っているということなんですよね。そこらへんを僕は、白州をやっている間ずーっと、「踊りはどうなるんだろう」というのが一番のテーマでした。もうやめようとなったのは、要するに、踊りの先行きがなくなったからです。こういう風に踊りを提案し、踊りをその土地で生まれさせてやる、それを繰り返しやっていく必要がないと思ったからです。だったらスタジオで踊りを作ればいいじゃん、くらいの投げやりな気分になりました。ちょっと好きな踊りから、他者意識というか、人のために踊りを考える気が一瞬なくなりました。自分の踊りが所属するカテゴリーをまず先に作ってしまうのです。それはないだろうと。だから、お金がないから踊れないって言ったりするんです。そんな言葉は不可能ですよ。踊りはあるものですからね。あなたが踊らなくても、踊りなんていくらでもあるよ。でも、そういう言葉で自己表明してしまうことは踊りにとって失礼なわけです。僕は白州の根底に踊りというものを置き、考え続けてきました。そこに、音楽もあり、美術もあったわけです。美術の人に対して、僕は踊りを見るようなつもりで美術が出来上がっていく姿を見ていたわけです。音楽の人にとっては、踊りが音楽に見えたりするわけです。それが一番面白い、そういう関係なんじゃないかなと思います。美術というのは、踊りが存在することで、美術という空間がどうなるんだろうかというのがすごく大きなテーマでした。自然とものとの関係だとすればですね。
名和:
当時の僕は美大の1年生で、「具体」や「もの派」が何なのかも分かっていませんでした。でも「美術家の家」で、もの派の世代の方々が「もの派というのは、ものとものの間に何かがあるということなんだ」と話しているのを聞いて、それが印象に残っていました。そのころ泯さんも「踊り手の肉体と見ている人の間にあるものが踊りなんだ」とおっしゃっていて、そこに繋がりがあるように感じられたのです。その後も僕は彫刻科で制作を続けてきましたが、そこでは単にオブジェクトをつくるだけではなく「物質と自分の身体がどう交流するか」「作品を見る人の中に何が残るのか」ということをずっと考えていました。こうした彫刻に対する意識も、白州での体験の中でつくられていったのだと思っています。
前田:
泯さんが、音楽と人、土地と人、美術と、そういうつなぎ役となっていた、身体で繋いでいく感じが面白いと思いました。
田中:
誤解されたくないのですが、僕は身体気象という言葉をだいぶ前から使っているのですが、これは、中心というものが常に空のように絶えず動いて回っている。時には消え、時には生まれているわけです。そういう人間同士のありようというのが、僕にとっては踊り的なんです。それが踊りといってもいいと思います。中心にとどまるということが僕にはありえないんです。泯さんがいたからというわけではなく、友達と縁が作り上げたものなのです。僕がやれることは僕流のやり方でやる、それがうまくハーモニーしていた、そこにやってくる若者たちもそのハーモニーに加わる。それが楽しかったんです。
今やろうとしたらとんでもない苦労をするんでしょう。
それぞれの〈白州〉体験
前田:
今日は会場の方にも白州を体験された、白州に深く関わった方たちもいらしていますが、坂口さんはいらっしゃいますか。
坂口:
坂口寛敏と申します。私は89年の2回目だと思いますが、榎倉康二さんから「坂口、白州で作品つくらないか」と誘いがあったので出かけていきました。私たちが車をどうやって山奥まで運ぶか困っているときに、泯さんが「飛ばせ!」と言ったことがずっと私の中に残っていて、カタログにはそのことについて書きました。仕事が終わって夜、榎倉さんが泯さんに「美術家はものが残るけど、踊る人はからだがなくなったらどうなるか」みたいなことを投げかけたのを思い出しています。そういうやりとりが何度も何度もあった中にいたのですが、やはり私個人としても、体験したのはそうやって、飛ばない車を傷つけず、小川に橋を作って渡して、それを再生させるということに自分の身体が関わったことで繋がっているのかなと感じます。
前田:
ありがとうございます。巻上さんともご共演されました大熊ワタルさん、今日いらしてるんですが、白州では芸能の源流がものすごく追求されていて、あらゆる音楽、音の人たちが集ったわけです。その中でも「白州ちんどん」というのが秀逸だったと思います。
大熊:
ありがとうございます。大熊ワタルと言います。僕も最初に白州に呼んでもらったのは巻上さんがおっしゃった、デレク・ベイリーのカンパニージャパンでした。ただフラフラしているだけだった自分も、素晴らしい人たちと遊ばせてもらい、最高な機会でした。さきほどフィルムを拝見していたら、まだ全然元気だったミルフォード・グレイブスが「東京だと自分のことを知っている人がいっぱいいるけど、ここには自分を知っている人は誰もいないけど、ここには土があるじゃないか」と話していて、ああそうだよなと思っていました。例えば、自意識的な説明をすると、0から場所を作って、音を1から出すという感覚もあるのですが、そこには環境があって、すごい山があって、水がすごく澄んでいて、そういう風景を見てると、自然と関係は始まっている。自分は何をしたらいいのかというのがどんどん見えてくる。そんな、すごくストンと決まってくるというか、空気がこんな透明なところがあるんだという、びっくりするぐらい、自分もどんどん透明になっていくみたいな不思議な感覚がありました。いつも夏が楽しいというか、学校の代わりに、一緒に学ぶような得難い場所だったと思います。音楽は特権的な何かではなくて、例えばご飯を食べに行く手作りの食堂があって、とれたての野菜があって、手作りのイスやテーブルがあって、そういう建築とかを色々と見ても、全部が等価だったですね。そういうのが響きあって、いろんな人が集まって、それが響きあってるいるような、そういうある種、夢の革命的な実験の場所のような、そんなイメージがありました。自分はここから学んで、どう自分のことをやろうかな、そんなアイデアをいっぱいもらった、最高の場所でした。
前田:
ありがとうございます。舞踊評論家の石井達朗さんもいらっしゃいます。白州ではダンスがいろんなところで行われていたわけですが、必ずその後に、ダンス談話とか、語らいの場を持たれていたんですね。そこで石井さんがいろんなダンサーたちの踊りについて、語られている映像とかもあり印象的でした。やはり、言葉の力というのが強く感じられる場だったんだなと思います。
石井:
石井達朗と申します。白州はダンスに限らず、前衛的なジャズミュージシャンから現代アートの先端を行っている彫刻家の方がいるかと思えば、大衆芸能があったり、南インドからクーリアッタムというギリシャ悲劇が現代に生き残っているというくらい、なかなか見られないものが山梨県の白州にやってきて、素晴らしい公演を見せるという、そういうごった混ぜなところと、私はいつも思います。白州みたいなフェスティバルは、これから可能なのかと思うと、絶対不可能な感じがするんですね。なぜ不可能かというと、我々はスマホとパソコンを持っていますよね。スマホとパソコンがあったら、白州は成り立たない。やっぱり、手で書いた地図をもって田んぼのあぜ道を歩いたり、そういうことによって、成り立っていた時間と空間があったと思います。それを、再現してほしいのですが、やっぱり不可能かなと感じます。
私が白州で印象に残っているのは、もちろんダンスも面白かったのですが、それよりも何よりも、パフォーマーの方と白州に来ている人たちとのボーダーラインがないんですね。それが要するに、我々が普段生活しているときの、たとえば男性・女性であるとか、世代がどうこうとか、あの人の仕事はこういう仕事をしている人だとか、そういうものが一切消えて、カブトムシがいる、クワガタがいる、という感じで、吉田さんがいる、石井さんがいる、っていう感じでいるわけです。要するに、呼吸している人たちが、ヒエラルキーが限りなく薄まった中で平等に生きている、そういう空間でした。パソコンとスマホの時代にどういうふうにしたら、ああいう空間が可能なのか、ときどき考えることがあります。みなさんも一緒に、泯さんも一緒に考えてください。ありがとうございます。
前田:
ありがとうございます。では、ボランティアをされていた方ということで、建築家の永山祐子さん、いかがですか。
永山:
本にも寄稿させていただきましたが、私が参加したのはたぶん、1994年かなと思います。私は象設計集団の樋口裕康さんのワークショップに友達何人かと参加しました。ムロをつくるというものでしたが、あんまり空気の流れが良くなくて、ムロにならないと、あとから文句を言われました。久住章さんに教わって、日干しレンガを作りました。すごくおもしろかったので、私だけ一人ボランティアをしようと思い、一度東京に帰ってからもう一回戻りました。その時、私は建築の学生でしたが、建築は考えてから5年後にやっとできあがるみたいな、そのタイムラグがすごくもどかしかったので、舞台美術に興味がありました。中上健次さんの「千年の愉楽」を観世栄夫と泯さんとやられていて、その舞台美術の手伝いをしました。私は黒子になって「千年の愉楽」の公演の時は、神社の縁の下に小さくなって、後ろからたくさん集めた落ち葉を投げる役でした。この場面に来たら投げるぞって、ずっとうずくまって、縁の下から、泯さんの背中と観世さんの背中をずっと見ていました。みんなが、うわー!って、見て感動している顔と、泯さんの背中と観世さんの背中を見て、私も震えるぐらい感動して、背中だけなのに、震えるような感覚でした。その時に、落ち葉を頑張って投げましたが、落ち葉なんていらないんじゃないかというくらい、空間が完成されていて、人間力に溢れていて。私が舞台美術で何かできるみたいな期待を持って行ったのに、いい意味で裏切られました。舞台なんかいらないし、空間もなんなら要らないし、超越したその姿をみて、私は本当に感動しました。もう一回ここに戻ってきてよかったなと、思いました。、舞台はやっぱり人が作るんだ、というのを目の当たりにしてしまったので、もう一度山を下りて、今度は建築事務所に行って、それから公共的な建築に携わっていく形で建築に戻りました。そういう人間力を見せつけられたことによって、私は次の道に背中を押してもらったような感じがします。まさに文章にも書いた通り、泯さんに背中を押されて、建築の道にもう一度行ってみようと思えたのです。あの夏があって、踏ん切りがついたという感じです。なかなか泯さんとはお話しする機会もなく、あこがれて遠巻きに見ていましたが、何度かお話しする機会があった時に、建築しています、と話したら、大きくなって帰って来いよと言われて。またその言葉に「めっちゃかっこいい~」と思って、じ~んときて、その時以来、今回初めて生でお会いできるので、すごく楽しみに来ました。
名和:
白州で落ち葉を投げていたボランティアが、今ではドバイ万博・日本館の設計など大活躍ですね。永山さんは僕と同年代で、白州への参加も同じ時期なんですよね。さらに展示に参加していただいた藤元明さんの奥さんでもいらっしゃいます。Sandwichを立ち上げる前年くらいにプロジェクトでお会いして、白州の話を通じて仲良くなり、Sandwichのリノベーションの際にも「どういうコンセプトがふさわしいか」「どういう場所にしたいのか」と一緒に議論していただきました。今回の展示にあたって、永山さんにはぜひ建築の立場からコメントをいただきたいと思っていたので興味深いですね。
田中:
ボランティアのつもりでやってきた人たちと、舞台を作ることは継続的にやってきています。今年も東京芸術劇場でやりますが、それに参加しているスタッフのほとんどが、白州のボランティアだった人たちです。自分の仕事を持ちながらも、劇場やるぞというと、やろうやろう、という感じでずっと続いてるんです。白州育ち、みたいな人はすごく多いと思います。
今日は会場の方にも白州を体験された、白州に深く関わった方たちもいらしていますが、坂口さんはいらっしゃいますか。
坂口:
坂口寛敏と申します。私は89年の2回目だと思いますが、榎倉康二さんから「坂口、白州で作品つくらないか」と誘いがあったので出かけていきました。私たちが車をどうやって山奥まで運ぶか困っているときに、泯さんが「飛ばせ!」と言ったことがずっと私の中に残っていて、カタログにはそのことについて書きました。仕事が終わって夜、榎倉さんが泯さんに「美術家はものが残るけど、踊る人はからだがなくなったらどうなるか」みたいなことを投げかけたのを思い出しています。そういうやりとりが何度も何度もあった中にいたのですが、やはり私個人としても、体験したのはそうやって、飛ばない車を傷つけず、小川に橋を作って渡して、それを再生させるということに自分の身体が関わったことで繋がっているのかなと感じます。
前田:
ありがとうございます。巻上さんともご共演されました大熊ワタルさん、今日いらしてるんですが、白州では芸能の源流がものすごく追求されていて、あらゆる音楽、音の人たちが集ったわけです。その中でも「白州ちんどん」というのが秀逸だったと思います。
大熊:
ありがとうございます。大熊ワタルと言います。僕も最初に白州に呼んでもらったのは巻上さんがおっしゃった、デレク・ベイリーのカンパニージャパンでした。ただフラフラしているだけだった自分も、素晴らしい人たちと遊ばせてもらい、最高な機会でした。さきほどフィルムを拝見していたら、まだ全然元気だったミルフォード・グレイブスが「東京だと自分のことを知っている人がいっぱいいるけど、ここには自分を知っている人は誰もいないけど、ここには土があるじゃないか」と話していて、ああそうだよなと思っていました。例えば、自意識的な説明をすると、0から場所を作って、音を1から出すという感覚もあるのですが、そこには環境があって、すごい山があって、水がすごく澄んでいて、そういう風景を見てると、自然と関係は始まっている。自分は何をしたらいいのかというのがどんどん見えてくる。そんな、すごくストンと決まってくるというか、空気がこんな透明なところがあるんだという、びっくりするぐらい、自分もどんどん透明になっていくみたいな不思議な感覚がありました。いつも夏が楽しいというか、学校の代わりに、一緒に学ぶような得難い場所だったと思います。音楽は特権的な何かではなくて、例えばご飯を食べに行く手作りの食堂があって、とれたての野菜があって、手作りのイスやテーブルがあって、そういう建築とかを色々と見ても、全部が等価だったですね。そういうのが響きあって、いろんな人が集まって、それが響きあってるいるような、そういうある種、夢の革命的な実験の場所のような、そんなイメージがありました。自分はここから学んで、どう自分のことをやろうかな、そんなアイデアをいっぱいもらった、最高の場所でした。
前田:
ありがとうございます。舞踊評論家の石井達朗さんもいらっしゃいます。白州ではダンスがいろんなところで行われていたわけですが、必ずその後に、ダンス談話とか、語らいの場を持たれていたんですね。そこで石井さんがいろんなダンサーたちの踊りについて、語られている映像とかもあり印象的でした。やはり、言葉の力というのが強く感じられる場だったんだなと思います。
石井:
石井達朗と申します。白州はダンスに限らず、前衛的なジャズミュージシャンから現代アートの先端を行っている彫刻家の方がいるかと思えば、大衆芸能があったり、南インドからクーリアッタムというギリシャ悲劇が現代に生き残っているというくらい、なかなか見られないものが山梨県の白州にやってきて、素晴らしい公演を見せるという、そういうごった混ぜなところと、私はいつも思います。白州みたいなフェスティバルは、これから可能なのかと思うと、絶対不可能な感じがするんですね。なぜ不可能かというと、我々はスマホとパソコンを持っていますよね。スマホとパソコンがあったら、白州は成り立たない。やっぱり、手で書いた地図をもって田んぼのあぜ道を歩いたり、そういうことによって、成り立っていた時間と空間があったと思います。それを、再現してほしいのですが、やっぱり不可能かなと感じます。
私が白州で印象に残っているのは、もちろんダンスも面白かったのですが、それよりも何よりも、パフォーマーの方と白州に来ている人たちとのボーダーラインがないんですね。それが要するに、我々が普段生活しているときの、たとえば男性・女性であるとか、世代がどうこうとか、あの人の仕事はこういう仕事をしている人だとか、そういうものが一切消えて、カブトムシがいる、クワガタがいる、という感じで、吉田さんがいる、石井さんがいる、っていう感じでいるわけです。要するに、呼吸している人たちが、ヒエラルキーが限りなく薄まった中で平等に生きている、そういう空間でした。パソコンとスマホの時代にどういうふうにしたら、ああいう空間が可能なのか、ときどき考えることがあります。みなさんも一緒に、泯さんも一緒に考えてください。ありがとうございます。
前田:
ありがとうございます。では、ボランティアをされていた方ということで、建築家の永山祐子さん、いかがですか。
永山:
本にも寄稿させていただきましたが、私が参加したのはたぶん、1994年かなと思います。私は象設計集団の樋口裕康さんのワークショップに友達何人かと参加しました。ムロをつくるというものでしたが、あんまり空気の流れが良くなくて、ムロにならないと、あとから文句を言われました。久住章さんに教わって、日干しレンガを作りました。すごくおもしろかったので、私だけ一人ボランティアをしようと思い、一度東京に帰ってからもう一回戻りました。その時、私は建築の学生でしたが、建築は考えてから5年後にやっとできあがるみたいな、そのタイムラグがすごくもどかしかったので、舞台美術に興味がありました。中上健次さんの「千年の愉楽」を観世栄夫と泯さんとやられていて、その舞台美術の手伝いをしました。私は黒子になって「千年の愉楽」の公演の時は、神社の縁の下に小さくなって、後ろからたくさん集めた落ち葉を投げる役でした。この場面に来たら投げるぞって、ずっとうずくまって、縁の下から、泯さんの背中と観世さんの背中をずっと見ていました。みんなが、うわー!って、見て感動している顔と、泯さんの背中と観世さんの背中を見て、私も震えるぐらい感動して、背中だけなのに、震えるような感覚でした。その時に、落ち葉を頑張って投げましたが、落ち葉なんていらないんじゃないかというくらい、空間が完成されていて、人間力に溢れていて。私が舞台美術で何かできるみたいな期待を持って行ったのに、いい意味で裏切られました。舞台なんかいらないし、空間もなんなら要らないし、超越したその姿をみて、私は本当に感動しました。もう一回ここに戻ってきてよかったなと、思いました。、舞台はやっぱり人が作るんだ、というのを目の当たりにしてしまったので、もう一度山を下りて、今度は建築事務所に行って、それから公共的な建築に携わっていく形で建築に戻りました。そういう人間力を見せつけられたことによって、私は次の道に背中を押してもらったような感じがします。まさに文章にも書いた通り、泯さんに背中を押されて、建築の道にもう一度行ってみようと思えたのです。あの夏があって、踏ん切りがついたという感じです。なかなか泯さんとはお話しする機会もなく、あこがれて遠巻きに見ていましたが、何度かお話しする機会があった時に、建築しています、と話したら、大きくなって帰って来いよと言われて。またその言葉に「めっちゃかっこいい~」と思って、じ~んときて、その時以来、今回初めて生でお会いできるので、すごく楽しみに来ました。
名和:
白州で落ち葉を投げていたボランティアが、今ではドバイ万博・日本館の設計など大活躍ですね。永山さんは僕と同年代で、白州への参加も同じ時期なんですよね。さらに展示に参加していただいた藤元明さんの奥さんでもいらっしゃいます。Sandwichを立ち上げる前年くらいにプロジェクトでお会いして、白州の話を通じて仲良くなり、Sandwichのリノベーションの際にも「どういうコンセプトがふさわしいか」「どういう場所にしたいのか」と一緒に議論していただきました。今回の展示にあたって、永山さんにはぜひ建築の立場からコメントをいただきたいと思っていたので興味深いですね。
田中:
ボランティアのつもりでやってきた人たちと、舞台を作ることは継続的にやってきています。今年も東京芸術劇場でやりますが、それに参加しているスタッフのほとんどが、白州のボランティアだった人たちです。自分の仕事を持ちながらも、劇場やるぞというと、やろうやろう、という感じでずっと続いてるんです。白州育ち、みたいな人はすごく多いと思います。
職業や立場を超えた人間同士の場
前田:
フェスティバルをはじめた方たちと、そしてそこから育っていった方たちが一堂に会する会をこのように持てて、本当に嬉しく思います。見るものに溢れていて、会場中にいろんな声がポリフォニックに響いている展覧会だと思います。ぜひ、またいらしていただければと思います。この外にあるお花とチョウチョも剣持さんの新境地ですので、そちらも是非、ご覧になっていただければと思います。
これが次の白州に向けての最初の一歩ということで、泯さん最後に一言ございますか。
田中:
次の白州…。たとえば音楽なら音楽、美術なら美術、踊りなら踊り、それぞれの表現があります。それからボランティア。ちょうど始めた88年頃はボランティアが何なのか皆さんに知れ渡っていなかった頃だと思います。ボランティアがどうなっていくのか、ボランティアの場がどういう風に変化していくのか、かなり誤解が生まれてきています。表現の場であることは確かですが、なんのための表現なのだろうか、利己的な問題なのだろうか、利他的な問題なのだろうか、きっかけは利他的であったとしても、それがすり替わっていくことになりかねないぞ、というようなことを思ってしまうような、場面がいっぱい見えてきているような気もします。白州は本当に手作りで、それからお金をかけない、そして、出会いの場所、本当の出会いの場所です。さきほど、食事の話もありましたが、食堂で朝から晩まで作ってる人もいるんです。フェスティバルの最後にお別れ会をやるのですが、ものすごいごちそうなんです。その人たちが台所から、全部自分たちで運んできて、みんなについでくれて。何百人もの最後の会をやるのですが、これもサントリーさんが飲料を提供してくださったおかげで、本当に盛り上がるお別れ会となりました。それは、ボランティアが最も元気に、一人ひとりが、自分が何者であるかということを思い切って喋れる、そういう場でもありました。
巻上:
やっぱり、すごいチームがあったんだなって、白州で思うことですね。
田中:
台所で、気が付くと大喧嘩してるわけですよ。つくるものとか、それから、つくるもののプロセスで大喧嘩したりとか。
巻上:
すごい料理ありましたからね。食べ物なんだろうか、みたいな時もあるんですよね。あれがいいんですよ。
田中:
表現者同士も、今はあまり見ないけど、本当に議論していた。ものすごい議論していた。僕の世代はもう、殴ったり殴られたり、っていうことは普通でしたから。それ見てみんなびっくりして、やめてください!っていうんだけど、これは普通なんだよ、って。
巻上:
泯さんみぞおちをプってやってましたもんね。
田中:
でも次の日は普通に喋れるんです。なぜなら、議論の末の話ですから。だから次の日は議論を続ければいいという。
名和:
僕が大学を卒業してアーティスト活動を始めた後くらいに、フラムさんが「大地の芸術祭」を始められました。それを皮切りに、日本の地方で芸術祭企画が急速に増えていきました。そこで採用されていたさまざまなフォーマット——例えば、ボランティアのシステムや、マップを使った屋外作品の周遊、地方の古民家を使ったインスタレーション——の源流には、白州における取り組みがあるように思います。僕たちの世代のアーティストはそうした地方の芸術祭に招待されることも多かったのですが、そのたびに「白州でこういうのあったよね」と毎回思い出していました。とはいえ、白州ほどの規模と密度でボランティア、出演者、地元の方々といったみんなが一緒になった交流というのは、多くの芸術祭に参加した今でも類を見ません。やはりあれは、人間力の集まりだったのかなと思いますね。
田中:
立場や自分の持ってる仕事をとっぱらって、人間同士が素直に関係を作っていく場というのが難しいですよね。家族でもそうだし。それになるべく近づけるためには、誰も威張ってはいけないと思います。年上だろうが、役が違うだろうが。それがたとえ一瞬であっても、その実感をみんなが持てば、次の瞬間は、変われるんじゃないか、というのが僕のばかな夢なんですけど。僕は、それを徹底して実行委員会でしゃべり続けていました。マニュアルで縛っちゃだめだということも最初から言っていたし、どんどんマニュアルは変わるべきだということも言っていました。白州でずっと、百姓をやって暮らしている、みんなが居なくなってもそこに居続ける人間の一人でしたから、そう言わしてくれ、と言っていました。お役所さんが来て言いづらいのであれば、それはだめだよと、みんなが喋れないならば、俺がしゃべる、というような、そんな感じでやっていました。それはすごく難しいと思います。
名和:
白州に集まっていた芸術家や音楽家たちの根底には、自分の意志で「踊ろう」とするモチベーションが共有されていました。だからこそ、多様な人々が集まる中でも、それぞれが自分を見失うことなく踊り合えていたのだと思います。近年、芸術祭の機会は格段に増えましたが、だからこそ芸術家たちは今一度「自分たちがそこでなにをしたいのか」を自覚する必要があるはずです。でなければ、自分の意志で踊るどころか、他人に踊らされるばかりになってしまうのではないでしょうか。
田中:
およばれされたと思っているとすぐにばれる、というのが白州。
巻上:
観客が厳しすぎる。音楽やるにしても、大変でした。
名和:
環境も厳しかったですよね。「ダンス白州」の最後の冬に栗林の中、テント一個で寝泊まりしたことを思い出します。寒くて寝られないなんて初めてで「こんなキャンプがあるんだ」って驚きました。
前田:
素晴らしい思い出ばかり。もっともっとお伺いしたいところですが、本当に貴重で大変刺激的なお話をどうもありがとうございました。
フェスティバルをはじめた方たちと、そしてそこから育っていった方たちが一堂に会する会をこのように持てて、本当に嬉しく思います。見るものに溢れていて、会場中にいろんな声がポリフォニックに響いている展覧会だと思います。ぜひ、またいらしていただければと思います。この外にあるお花とチョウチョも剣持さんの新境地ですので、そちらも是非、ご覧になっていただければと思います。
これが次の白州に向けての最初の一歩ということで、泯さん最後に一言ございますか。
田中:
次の白州…。たとえば音楽なら音楽、美術なら美術、踊りなら踊り、それぞれの表現があります。それからボランティア。ちょうど始めた88年頃はボランティアが何なのか皆さんに知れ渡っていなかった頃だと思います。ボランティアがどうなっていくのか、ボランティアの場がどういう風に変化していくのか、かなり誤解が生まれてきています。表現の場であることは確かですが、なんのための表現なのだろうか、利己的な問題なのだろうか、利他的な問題なのだろうか、きっかけは利他的であったとしても、それがすり替わっていくことになりかねないぞ、というようなことを思ってしまうような、場面がいっぱい見えてきているような気もします。白州は本当に手作りで、それからお金をかけない、そして、出会いの場所、本当の出会いの場所です。さきほど、食事の話もありましたが、食堂で朝から晩まで作ってる人もいるんです。フェスティバルの最後にお別れ会をやるのですが、ものすごいごちそうなんです。その人たちが台所から、全部自分たちで運んできて、みんなについでくれて。何百人もの最後の会をやるのですが、これもサントリーさんが飲料を提供してくださったおかげで、本当に盛り上がるお別れ会となりました。それは、ボランティアが最も元気に、一人ひとりが、自分が何者であるかということを思い切って喋れる、そういう場でもありました。
巻上:
やっぱり、すごいチームがあったんだなって、白州で思うことですね。
田中:
台所で、気が付くと大喧嘩してるわけですよ。つくるものとか、それから、つくるもののプロセスで大喧嘩したりとか。
巻上:
すごい料理ありましたからね。食べ物なんだろうか、みたいな時もあるんですよね。あれがいいんですよ。
田中:
表現者同士も、今はあまり見ないけど、本当に議論していた。ものすごい議論していた。僕の世代はもう、殴ったり殴られたり、っていうことは普通でしたから。それ見てみんなびっくりして、やめてください!っていうんだけど、これは普通なんだよ、って。
巻上:
泯さんみぞおちをプってやってましたもんね。
田中:
でも次の日は普通に喋れるんです。なぜなら、議論の末の話ですから。だから次の日は議論を続ければいいという。
名和:
僕が大学を卒業してアーティスト活動を始めた後くらいに、フラムさんが「大地の芸術祭」を始められました。それを皮切りに、日本の地方で芸術祭企画が急速に増えていきました。そこで採用されていたさまざまなフォーマット——例えば、ボランティアのシステムや、マップを使った屋外作品の周遊、地方の古民家を使ったインスタレーション——の源流には、白州における取り組みがあるように思います。僕たちの世代のアーティストはそうした地方の芸術祭に招待されることも多かったのですが、そのたびに「白州でこういうのあったよね」と毎回思い出していました。とはいえ、白州ほどの規模と密度でボランティア、出演者、地元の方々といったみんなが一緒になった交流というのは、多くの芸術祭に参加した今でも類を見ません。やはりあれは、人間力の集まりだったのかなと思いますね。
田中:
立場や自分の持ってる仕事をとっぱらって、人間同士が素直に関係を作っていく場というのが難しいですよね。家族でもそうだし。それになるべく近づけるためには、誰も威張ってはいけないと思います。年上だろうが、役が違うだろうが。それがたとえ一瞬であっても、その実感をみんなが持てば、次の瞬間は、変われるんじゃないか、というのが僕のばかな夢なんですけど。僕は、それを徹底して実行委員会でしゃべり続けていました。マニュアルで縛っちゃだめだということも最初から言っていたし、どんどんマニュアルは変わるべきだということも言っていました。白州でずっと、百姓をやって暮らしている、みんなが居なくなってもそこに居続ける人間の一人でしたから、そう言わしてくれ、と言っていました。お役所さんが来て言いづらいのであれば、それはだめだよと、みんなが喋れないならば、俺がしゃべる、というような、そんな感じでやっていました。それはすごく難しいと思います。
名和:
白州に集まっていた芸術家や音楽家たちの根底には、自分の意志で「踊ろう」とするモチベーションが共有されていました。だからこそ、多様な人々が集まる中でも、それぞれが自分を見失うことなく踊り合えていたのだと思います。近年、芸術祭の機会は格段に増えましたが、だからこそ芸術家たちは今一度「自分たちがそこでなにをしたいのか」を自覚する必要があるはずです。でなければ、自分の意志で踊るどころか、他人に踊らされるばかりになってしまうのではないでしょうか。
田中:
およばれされたと思っているとすぐにばれる、というのが白州。
巻上:
観客が厳しすぎる。音楽やるにしても、大変でした。
名和:
環境も厳しかったですよね。「ダンス白州」の最後の冬に栗林の中、テント一個で寝泊まりしたことを思い出します。寒くて寝られないなんて初めてで「こんなキャンプがあるんだ」って驚きました。
前田:
素晴らしい思い出ばかり。もっともっとお伺いしたいところですが、本当に貴重で大変刺激的なお話をどうもありがとうございました。
Related article
Recent Blog
Archives
ICHIHARA×ART×CONNECTIONS-交差する世界とわたしレポート
2023.09.26
フィリピンからアーティストがやってくる!「ゴミをアートにいきかえらせよう!」アウトリーチレポート
来春開催予定の企画展「ICHIHARA×ART×CONNECTIONS…
MORE
レポート
2023.08.15
フォーラム「湖の記憶、川の思い出」レポート
8月11日に当館多目的ホールにて、フォーラム「湖の記憶、川の思い出」が…
MORE
レポート
2023.07.15
【市原湖畔美術館開館10周年記念】地域へ、世界へ。わたしたちの10年
2023年夏、市原湖畔美術館は開館10周年を迎えました。開館してからこ…
MORE
レポート
2023.07.15
【市原湖畔美術館開館10周年記念】アーティストメッセージー10周年によせて
10年という歳月の中で、当館はお客様や地域の方々などさまざまな人たちに…
MORE
レポート
2022.06.03
オープニングトーク 金氏徹平×村田沙耶香「変容する世界の中で」
金氏徹平さんと芥川賞作家の村田沙耶香さんをゲストにお招きして、それぞれ…
MORE
レポート
2022.01.15
湖の記憶を語る会
高滝湖ができる以前の地域についてーー集落のこと、生業のこと、祭りのこと…
MORE